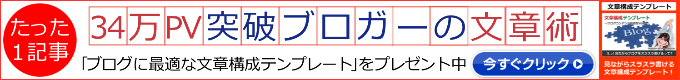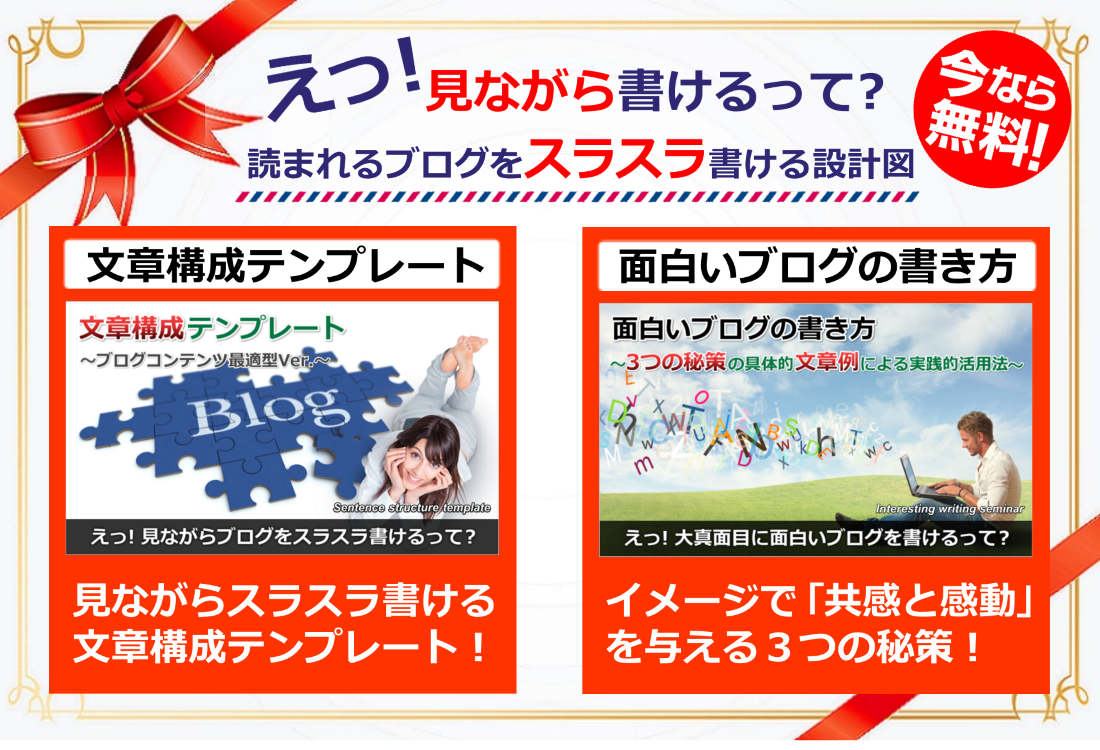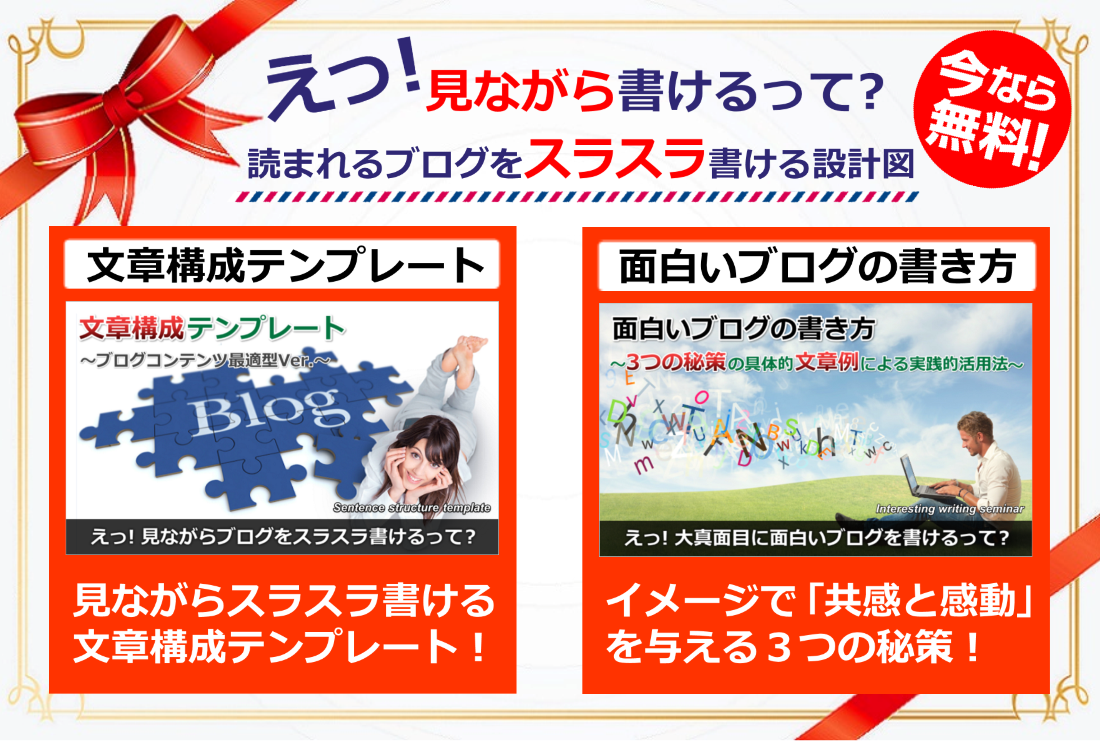体言止めには、文章にイメージ的な余韻を感じさせたり、
リズムを持たせる効果があります。
語尾の使い方によって、大きく上手い下手が分かれてしまいますからね。
ここでは、体言止めの「例文」を使い、
その「意味と使い方」を徹底的に解説します。
まずは、体言止めとは何なのかという部分から見ていきましょう。
※躍動する文章術の秘密をパワーブロガーが遂に明かします。
⇒ ブログの書き方講座【たった1記事34万PV突破ブロガーの文章術】
目次
体言止めとは?その意味をわかりやすく解説
体言止めとは、名詞、代名詞、数詞などで文章を止める、
修辞技法(比喩・直喩法・隠喩法・倒置法・体言止め等)の中の1つの種類を指します。
例えば、語尾でよく使われる「です」「ます」などで終わらせるのではなく、
下記のように、名詞、代名詞、数詞などで文章を止めて終わらせる技法です。
【代名詞】おれ・あいつ・どれ・みんな・わたし・あなた、など。
【数詞】一人・三匹・五冊・三台・一つ・二頭・三枚、など。
「体言」の意味は、主に「名詞」を表し、他に、
「代名詞」「数詞」を併せた3つを「体言」とするのが一般的です。
つまり、名詞、代名詞、数詞である、
「体言」を「止める」ことが「体言止め」という意味なのです。
体言止めの使い方

体言止めとは、和歌・俳諧などで、
語尾を名詞・代名詞・数詞などで止める使い方のこと。
例えば、「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」はご存じですよね。
「法隆寺」が名詞で終わっています。
こういった語尾を体言止めと言います。
俳句で見ると、とても特殊なもののように思えますが、
実は、普通の文章でも体言止めに変えられる部分は多いです。
では、実際の例文で体言止めを解説していきますね。
体言止めの例文
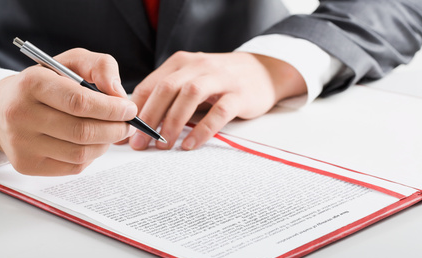
まずは、下記の例文を読んでみてください。
富士山頂から見たご来光と雲海です。
たどり着くまでの苦労を、全て忘れてしまうほどの光景でした。
この例文を体言止めにしてみました。
それは富士山頂から見たご来光と雲海。
たどり着くまでの苦労を、全て忘れてしまうほどの光景でした。
この体言止めの例文では、
特にイメージ的な余韻を感じますよね。
ではこれはどうでしょう。
なんといっても最高だったのは、
露天風呂から見える夕陽でした。
食事もとても美味しく、ゆっくりできたお休みでした。
この例文を体言止めにしてみました。
なんといっても最高だったのは、露天風呂から見える夕陽。
食事もとても美味しく、ゆっくりできたお休みでした。
この体言止めの例文では、
特にリズムに変化を感じるはずです。
前者は初心者によくありがちな連続語尾、
「~した」の3連続での使用によって単調ですよね。
「~夕陽でした」を体言止めにして、「~夕陽」にすることで、
単調なイメージもなくなり、後者ではリズムを感じるはずです。
「~した」に限らず、語尾の連続使用を回避する意味で、
体言止めを使うことも可能。
ただし、体言止めを使いすぎるのは良くないし、
使い方にも注意が必要です。
※同一語尾の連続使用は稚拙な文章になりがちです。
⇒ 稚拙な文章とは?ブログ記事にありがちな5つの事例
体言止めの3つの効果
体言止めを使うことで、
読み進めやすくなると共に、注意を惹くことができるようになります。
文章を読んでいただくには、ストレスを与えず、
尚且つ、飽きさせないことが大切ですからね。
ここでは、体言止めの効果を、3つお伝えします。
ストレスを感じなくなることで読み進めやすくなる
体言止めを使うことで、ストレスなく読み進めやすくなります。
下記の例文を読んでみてください。
渡月橋辺りから見るのがおすすめで、桂川の周りに群生していて、
赤や黄色の色合いがとても美しく毎年見るたびに心が癒されるようです。
この例文では、句点までの一文が長く、
ダラダラしているためストレスを感じるのではないでしょうか。
この例文を体言止めにして区切ってみました。
渡月橋辺りから見るのがおすすめで、桂川の周りに群生しています。
赤や黄色の色合いがとても美しく毎年見るたびに心が癒されるようです。
この体言止めの例文では、句点までの長い一文を区切り、
体言止めを使うことで、ダラダラした文章ではなくなり、
ストレスを感じにくくなっているはずです。
このように、句点までの一文が長くダラダラした文章になってしまう場合、
体言止めを効果的に使うことで、ストレスを感じず読み進めやすくなるのです。
リズムを感じることで飽きずに読める
体言止めを効果的に使うと、リズムを感じるので飽きずに読めるようになります。
下記の例文を読んでみてください。
ぽかぽか陽気で気持ちの良い小春日和でした。
ベンチに座っていると眠くなりました。
この例文では、同じ語尾「~した」が3連続で使われていることで、
リズムが無く文章が稚拙に感じられるのではないでしょうか。
この例文を体言止めにして区切ってみました。
ぽかぽか陽気で気持ちの良い小春日和。
ベンチに座っていると眠くなりました。
この例文では、
語尾の「した」の3連続の間に体言止めを挟むことでリズムを持たせています。
このように、
同じ語尾が連続して使われていることで、
リズムが無く文章が稚拙に感じられるような場合、
体言止めを効果的に使うことで飽きずに読める文章となるのです。
注意を惹くことで離脱を防げる
体言止めを使えば、注意を惹くことで離脱を防ぐことができます。
下記の例文を読んでみてください。
その眩しさと広大さに時を忘れ、穏やかな時間が流れていきました。
この例文は、特に問題のある文章ではありません。
しかし、こういった場合でも、体言止めを効果的に使うことで、
下記のように、注意を惹く文章にすることができます。
見ているとその眩しさと広大さに時を忘れ、穏やかな時間が流れていきました。
体言止めで区切り、注意を惹くことで、その先を読み進めてもらいやすくなります。
特に問題がある文章では無くても、
体言止めを使うことで、注意を惹いて離脱を防ぐ効果をもたらすのです。
体言止めの注意点

体言止めを使うことで、文章は読み進めやすくなり、
注意を惹くこともできますが注意点があります。
それは、使いすぎると逆効果となってしまうことです。
下記の例文を読んでみてください。
家族みんなで過ごしたエメラルドグリーンのビーチです。
離島に行くまでの船がかなり揺れて大変でしたが、
真っ白は砂浜で流れる時間が最高の思い出になりました。
例えば、この例文で、
体言止めばかりを使ってみるとこうなります。
それは、家族みんなで過ごしたエメラルドグリーンのビーチ。
かなり揺れて大変だった離島に行くまでの船。
真っ白は砂浜で流れる時間が最高の思い出。
この体言止めばかりの例文は、
文章としてわかりにくく違和感さえ感じますよね。
俳句や歌詞ではないので、
ここまで、体言止めを多用してしまうと、
逆に文章が単調になり、リズムも感じなくなります。
この後に、補足で文章を加えないと何が言いたいのか捉えずらいです。
このように、使い方次第では、
逆効果となってしまいますので、使い過ぎには注意してください。
ビジネス文で体言止めを使う場合
体言止めは文章の表現を広げてくれますが、使うシーンを間違えてはいけません。
それは、ビジネス文では多くの場合、
体言止めを使うことで伝えたいことがわかりずらくなることがあるからです。
伝えたいことが正確に伝わらない例
例えば、下記の例文を読んでみてください。
これを体言止めにすると下記のようになります。
体言止めにした場合、伝えたいニュアンスが変わってしまう場合があります。
「来月の定例会では地区委員が決定すると思います」
は、「思います」という100%確実ではないニュアンスです。
それに対し「来月の定例会では地区委員が決定」は、
100%確実な決定に変わってしまうのです。
体言止めにしたほうがわかりやすい箇条書き例
ビジネス文で情報を伝えるなどの場合、
体言止めで箇条書きにしたほうが、伝わりやすい場合があります。
例えば、下記の例文を読んでみてください。
開催場所は今回初めての割烹料理○○店です。
参加費用は1人4,500円です。
これを体言止めにすると下記のようになります。
開催場所は今回初めての割烹料理○○店。
参加費用は1人4,500円。
ただし、こういう場合は、
下記のように箇条書きにしたほうが伝わりやすくなります。
・日時:6月12日10時00分
・場所:割烹料理○○店
・参加費用:1人4,500円
ビジネス文では、体言止めを使うにしても、
箇条書きにしたほうが良い場合があります。
見やすく正確に伝えることが出来るため、
ビジネス文で情報を伝えるなどの場合、
箇条書きを使うことも頭に入れておきましょう。
体言止めに句読点は必要?
体言止めは、通常の文章中で使う場合、基本的には句読点が必要です。
句読点が無いと、文章に区切りが無くなり読みずらいですからね。
例えば、下記の句点「。」の例文を読んでみてください。
その迫力にとても驚いた夏の夜でした。
このように、体言止めでは句点「。」は必要です。
ただし、「箇条書き」などでは句点「。」は基本的に使いません。
例えば、下記のような場合です。
・開宴の辞
・主賓の挨拶と乾杯
・ケーキ入刀
・食事開始
2日目:那覇市内のホテル
3日目:読谷村の民泊
体言止めの反対語とされる用言止めって何?
「体言止め」に対し「用言止め」という言葉が、
反対語として表現されている場合があります。
しかし、「体言止め」の反対語が「用言止め」として、
正式に用いられている訳ではありません。
「体言」とは、名詞、代名詞、数詞などのこと。
「用言」とは、動詞、形容詞、形容動詞などのこと。
名詞、代名詞、数詞で「止める」ことを体言止め。
動詞、形容詞、形容動詞で「終える」ことを用言止めと言うのです。
例えば、
これは体言止めです。
用言止めとは下記のようなものになります。
青森といえばリンゴである。
青森といえばリンゴだ。
これははすべて用言止めになります。
また、一般的な文章でよく使われる「です・ます」も用言止めに分類されます。
青森のねぶた祭に行きます。
体言止めと倒置法の違い
体言止めと同じ修辞技法のひとつに「倒置法」という表現技法があります。
この2つの違いを分かりやすくいうと、
体言止めは、名詞、代名詞、数詞などで文章を止める技法。
倒置法は、文章の前と後ろを入れ替える技法のことです。
倒置法の場合は、語尾が名詞、代名詞、数詞などで終わりませんので、
語尾で、体言止めではないことが分かります。
例えば、下記の例文を読んでみてください。
これを倒置法で表現すると下記のようになります。
語順を入れ替えることで、印象が変わったはずです。
小説やキャッチコピー、俳句などでも、よく使われる、
印象を変えるための表現技法を倒置法と言います。
これを名詞の「君」で止めると下記のように体言止めになります。
体言止めはイメージ的な余韻を感じるリズムを作る
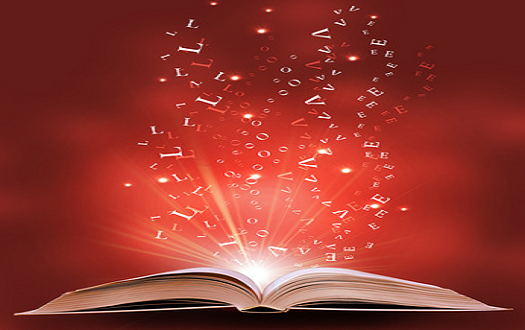
ブログ記事では、一般の書籍などとは違い、
まず読み進められることが重要です。
ネットという特性上、
すぐにサヨナラされるリスクがありますからね。
そういった意味でも、リズムに気を配る手段として、
体言止めは効果をもたらすでしょう。
※「文字レイアウト」を変えるだけでもリズムは整います。
⇒ ブログの書き方!たった1記事で18万人に読まれる基礎テクニック
体言止めは、全体的なバランスを考えて、
何度も読み返して違和感がないか確かめて活用してください。
文章の上手い人は「リズム」がしっかりできています。
その域に達するためには、
自分の書いたものを何度も考察する意識は不可欠。
体言止めを意識的に活用することで、
イメージ的な余韻を感じるリズム感ある文章を目指してくださいね。